この記事では、現役AWSエンジニアである筆者が実際に「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)」を触ってみた率直な感想を共有します。
AWSとの比較を交えながら、OCIの「意外と良かった点」と「正直に言って使いづらかった点」を具体的に解説します。
これからマルチクラウドを学ぼうとするエンジニアや、AWS以外の選択肢を検討している方にとって参考にしていただければと思います。
OCI(Oracle Cloud Infrastructure)とは
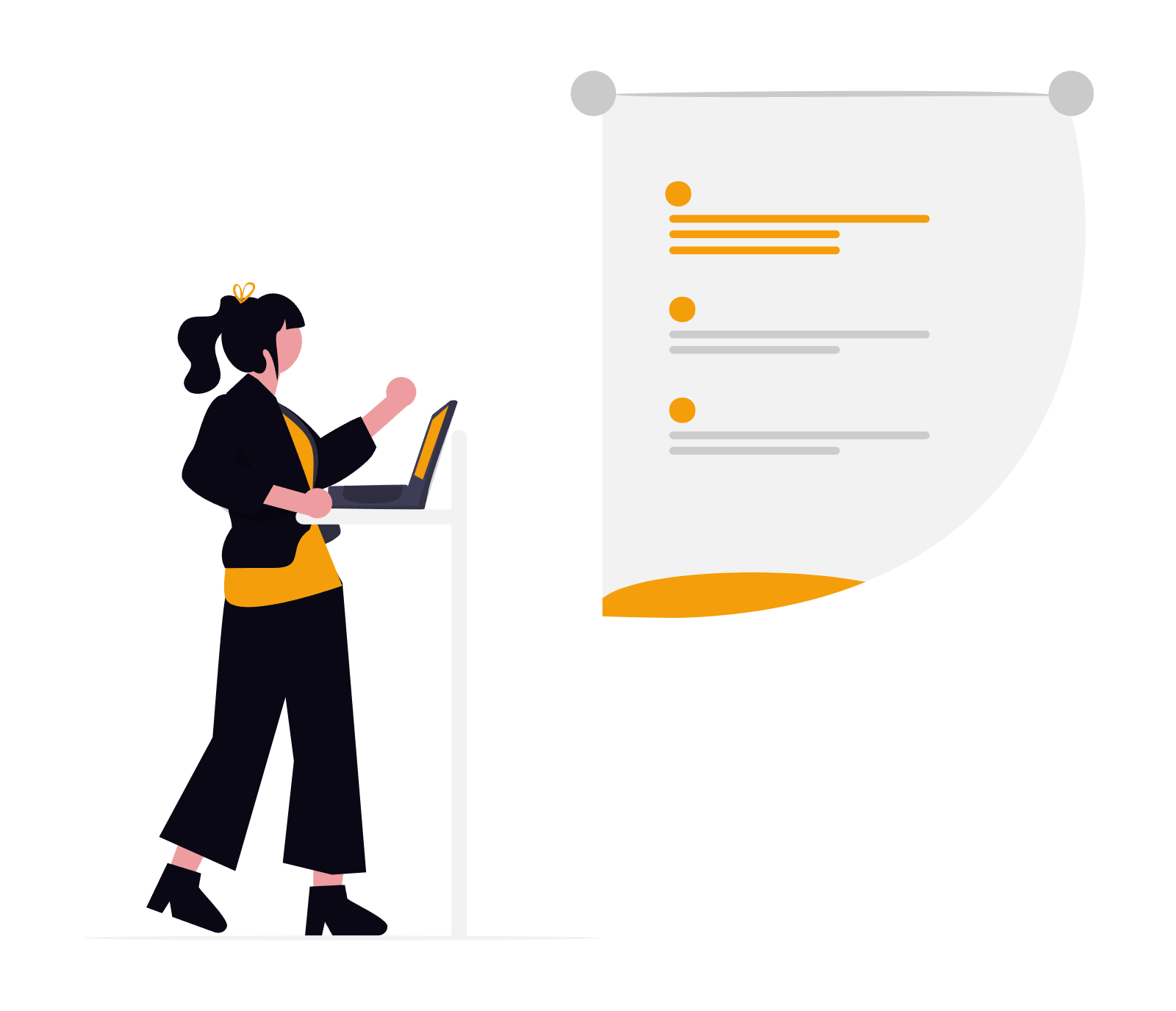
まずは、OCI(Oracle Cloud Infrastructure)とは何かを整理しておきます。
名前の通り、Oracle社が提供するクラウドサービスで、AWSやAzureと同じくIaaS型のクラウドプラットフォームです。
AWSエンジニアの視点から見ると、意外と共通点が多く、構成や概念も理解しやすい部分があります。
OCIの特徴
OCIは、Oracleが提供するパブリッククラウドで、コンピュート・ストレージ・ネットワーク・データベースといった主要なクラウド要素を包括的に提供しています。
特に注目すべきは、Oracle Databaseとの統合の強さで、エンタープライズシステムとの親和性が高い点です。
AWSのVPCに相当する「VCN(Virtual Cloud Network)」や、EC2に近い「Compute Instance」など、用語や概念が非常に似ており、AWS利用者であれば構成図を見た瞬間に理解できます。
また、Oracle特有の「Availability Domain(可用性ドメイン)」という仕組みで冗長化を実現しており、リージョン単位での信頼性も高いです。
近年はマルチクラウド戦略の一環として、AWSとOCIを連携させる事例も増えており、クラウドエンジニアが知っておく価値のあるプラットフォームです。
後発クラウド
OCI(Oracle Cloud Infrastructure)は、AWSやAzure、GCPと比べると明確に「後発クラウド」に位置づけられます。
初期リリースは2016年頃で、AWSが2006年にサービスを開始してから約10年の差があります。
そのため、OCIは他社クラウドの成功と課題を分析したうえで設計されており、アーキテクチャの思想やセキュリティモデルに“後発ならではの洗練”が見られます。
具体的には、仮想ネットワークの分離設計(VCN)が最初からゼロトラストを前提としており、IAMのきめ細かな制御や暗号化が標準装備されています。
また、パフォーマンス面でもネットワーク帯域を固定ではなくスケーラブルに設計しており、従来型のクラウドよりも一貫した通信速度を実現しています。
一方で、後発ゆえにエコシステムや導入事例が少ないという特徴もあります。
つまりOCIは「成熟度では劣るが、構造的には最新設計のクラウド」と言える存在です。
触って分かったOCIの良い点

OCIを実際に触ってみると、AWSとは異なる特徴が多く見つかりました。
良かった点をまとめます。
料金が安い
最も驚いたのは、OCIの料金が全体的にかなり安いことです。
同スペックのインスタンスをAWSと比較すると、Compute(EC2相当)は2〜3割ほど安く、ブロックストレージやネットワーク転送料も割安に設定されています。
特に嬉しいのは「Always Free」枠の内容が手厚い点です。
例えば、VM.Standard.E2.1.Micro(1 OCPU / 1GB RAM)を常時無料で利用でき、ストレージやロードバランサも無料枠に含まれています。
AWSのFree Tierよりも制約が緩く、実験や小規模検証を行うには十分なスペックです。
加えて、リージョン間通信やEgressコストも低く、グローバルな構成でもコストを抑えられます。
NAT GWが無料であることも良い点ですね。
学習目的だけでなく、個人開発やPoC用途でも「とりあえず触ってみよう」と思える価格感です。
ただし、AWSで言う、「t2.micro」など安いインスタンス同士と比べるとそこまで価格の差はありません。
商用レベルのサーバーを利用する際はOCIの恩恵を受けられるはずです。
フレキシブルインスタンス
OCIの特徴のひとつが「フレキシブルインスタンス」です。
AWSのt系やm系のようにインスタンスタイプを固定せず、CPUとメモリを任意の値で設定できるのが大きな違いです。
例えば、OCPU(Oracle CPU)を0.25単位で調整でき、RAM容量も自由に設定可能です。
これにより、検証環境を「CPU 1.5 / RAM 6GB」といった細かいチューニングで最適化できます。
AWSだとインスタンスタイプごとの固定構成になるため、余剰リソースが発生しやすいですが、OCIは無駄を極限まで減らせます。
また、インスタンス作成後にスケールアップ/ダウンも柔軟に行えるため、開発段階での調整が容易です。
リソース効率とコスト最適化を両立できる設計思想は、非常に好印象でした。
基礎資格試験は無料 & いつでも受験可能
OCIのもう一つの強みは、認定資格試験が無料で受験できる点です。
AWSの認定試験が1万円以上かかるのに対し、OCIの「Foundations Associate(基礎資格)」は公式サイトから誰でも無料受験可能です。
しかも、試験はオンライン完結で、日時指定も不要。
アカウント登録後すぐに受けられ、合格すれば公式認定証も発行されます。
初学者にとって「資格を取るハードルが低い」ことは、モチベーション維持に非常に効果的です。
内容もAWS CLF(クラウドプラクティショナー)と似ており、クラウド基礎を体系的に学べます。
マルチクラウド人材を目指す第一歩としても最適で、「AWS+OCI両方理解している」という差別化ポイントを簡単に得られるのは大きな魅力です。
触って分かったOCIの悪い点
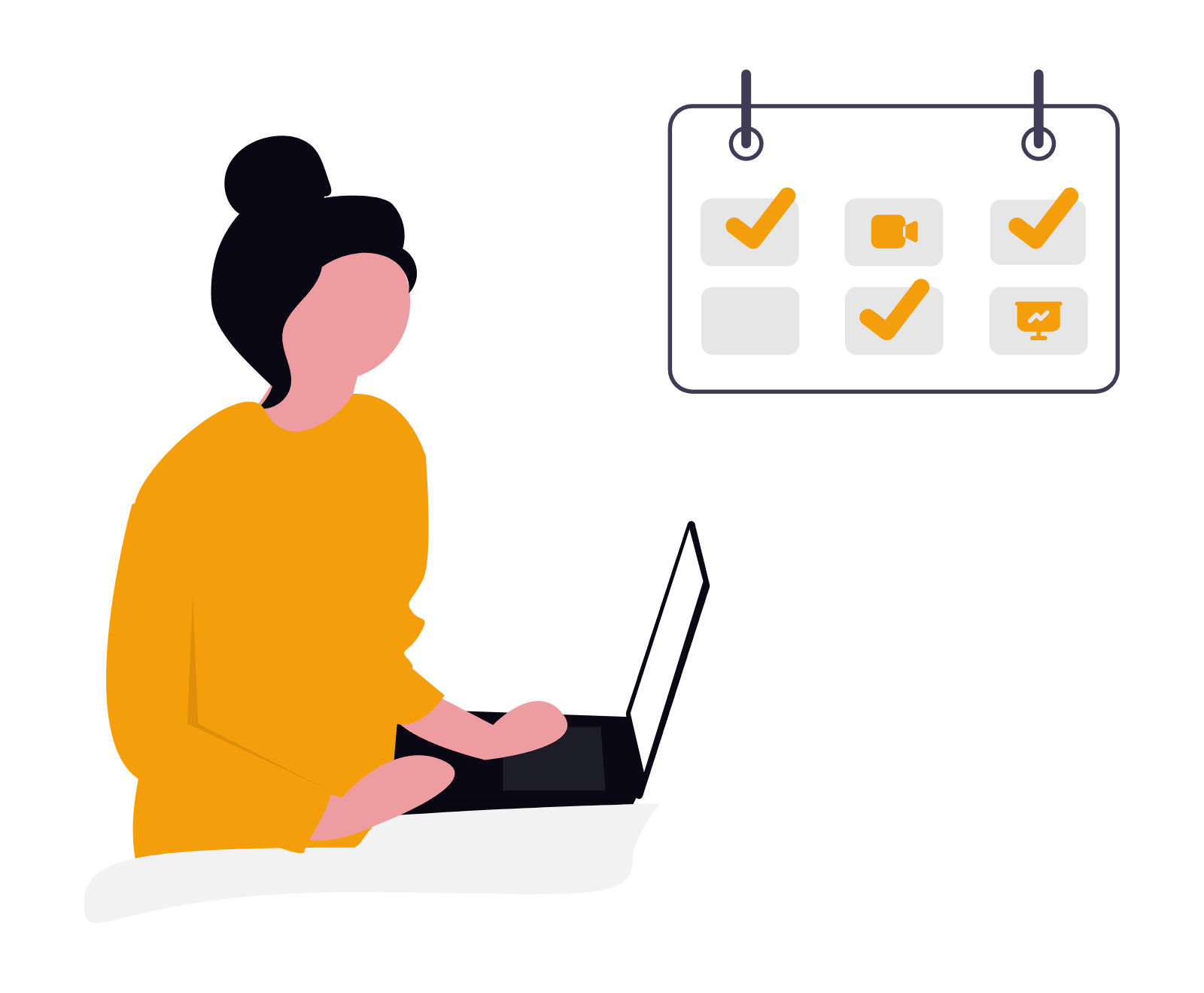
一方で、OCIを使ってみるとAWSでは感じない不便さも目立ちました。
続けてご紹介します。
そもそも登録ができない
OCI最大の難点は、アカウント登録が非常に通りにくいことです。
クレジットカード認証の精度が厳しく、国内発行カードでもエラーになることが多発します。
筆者も実は個人アカウントは未だ登録できていません。(会社のアカウントを使って触りました)
これまで30回以上申請しましたが、謎のエラーで登録不可、問い合わせをしても「分からない」の1点張りです。。
他の人もかなり苦労されているようです。
https://www.reddit.com/r/oraclecloud/comments/r487ay/i_cant_create_my_free_tier_account/?tl=ja
AWSのように「数分でアカウント開設」とはいかず、開始までの心理的・時間的コストが高いです。
また、住所や電話番号などの入力フォームも細かく、英語表記にしないと弾かれることもあります。
公式サポートも英語対応が多く、初学者にはハードルが高いと感じました。
クラウドを「触ってみる」段階でつまずくため、学習の入口としてはAWSより明らかに不親切です。
無料利用枠が使えない
OCIには「Always Free」枠がありますが、実際には利用できないケースが多くあります。
特定リージョンではリソースが枯渇しており、無料枠のインスタンスを作成しようとすると「容量がありません」と表示されます。
特に東京リージョンは混雑しており、常に使用不可の状態が続いています。
また、「Always Free」枠のスペックの低いインスタンスは立ち上げることができますが、スペックが低すぎて初期状態ではSSHもできません。
衝撃ですよね。
そのため、せっかく無料枠を目当てに登録しても、実際にインスタンスを立ち上げられないことがあるのです。
一応、他リージョン(シンガポールなど)なら動くこともありますが、ネットワーク遅延が大きく学習用には不向き。
「無料で試せる」と謳っていても、実際にはハードルが高いのが現実です。
GUIがもっさりしている
OCIコンソールの操作感も、AWSと比較するとやや重く感じます。
画面遷移のたびに読み込み時間が長く、レスポンスが安定しません。
特にリソース一覧画面ではテーブル更新に数秒かかり、ストレスを感じる場面が多いです。
また、デザインも直感的とは言えず、メニュー階層が深い点も難点です。
AWSマネジメントコンソールに慣れていると、「この設定どこ?」と探し回ることになります。
さらに、サービス名や用語がAWSと微妙に異なるため、マッピングにも時間がかかります。
CLIやTerraformを使えばある程度カバーできますが、GUI前提で学習する初心者には不向きです。
UI改善が進めば魅力的なプラットフォームになるものの、現時点ではAWSの圧勝と感じました。
OCIスキルを習得しても単価アップにつながらない
OCIを学んでも、現状ではフリーランスやSES案件での単価アップはほとんど期待できません。
実際、ほんの少ししか上がりません。
また、AWSやAzureが案件の大半を占める中で、OCIは公共系やOracle既存ユーザーへの限定導入が中心であり、案件数そのものが少ないのが現状です。
また、エンジニア単価もAWS認定保持者に比べて評価されにくく、同等スキルで見積もっても報酬差が出にくい傾向にあります。
クラウドスキルとしての評価軸もまだ標準化されておらず、「OCIができる=高単価」とはならないのが実情です。
そのため、OCIを学ぶ意義は報酬よりも「マルチクラウド知見の拡張」や「AWSとの比較理解」にあります。
キャリア投資としては有効ですが、収益性を目的にするならAWS・Azureの方が依然として優位です。
ただ、料金の安さはピカイチなので、今後ユーザーが流れて案件が増えていくと単価が上がっていくと思われます。
まとめ
OCI(Oracle Cloud Infrastructure)は、AWSエンジニアが触れてみる価値のあるクラウドです。
コストの安さやフレキシブルなインスタンス、無料資格制度などは大きな魅力ですが、一方で登録・操作性の面では課題が多いのが実情です。
特に「始めるまでの難しさ」が最大のネックであり、学習用途であればAWSの方が圧倒的に快適です。
しかし、OCIを理解することでマルチクラウド構成やコスト最適化の視野が広がるため、中級者以上にはおすすめできます。
AWS中心のエンジニアであっても、一度OCIを触っておくことで、設計力と視座が確実に高まります。
「使いづらいけれど、知っておく価値がある」──それが、筆者の率直な結論です。
