最近では、「オブザーバビリティ」という言葉が頻繁にみられるようになりましたね。
インフラだけでなく、アプリ側やDB側といったアプリケーション全体を測定する考え方でDataDogやNewRelicなどのAPMツールを利用することで実現できます。
今回は、AWSエンジニアがNewRelicを個人で導入・利用してみましたので、使い勝手や良い点・悪い点をご紹介します。
結論:導入は可能だが「一人では持て余す」

AWSエンジニアとしてNewRelicを個人導入した結果、セットアップ自体は容易だが、運用を一人で回すのは現実的に厳しいという結論に至りました。
NewRelicは「できることが多すぎる」ツールです。アプリ、インフラ、ログ、UXなど、全方位での監視が可能ですが、それぞれの設定と分析に時間を取られます。
NewRelic 個人利用は、監視の勉強や小規模サービスの可視化には最適ですが、本格的な運用管理には体制整備が不可欠だなと感じました。
なぜNewRelicの個人利用が難しいのか
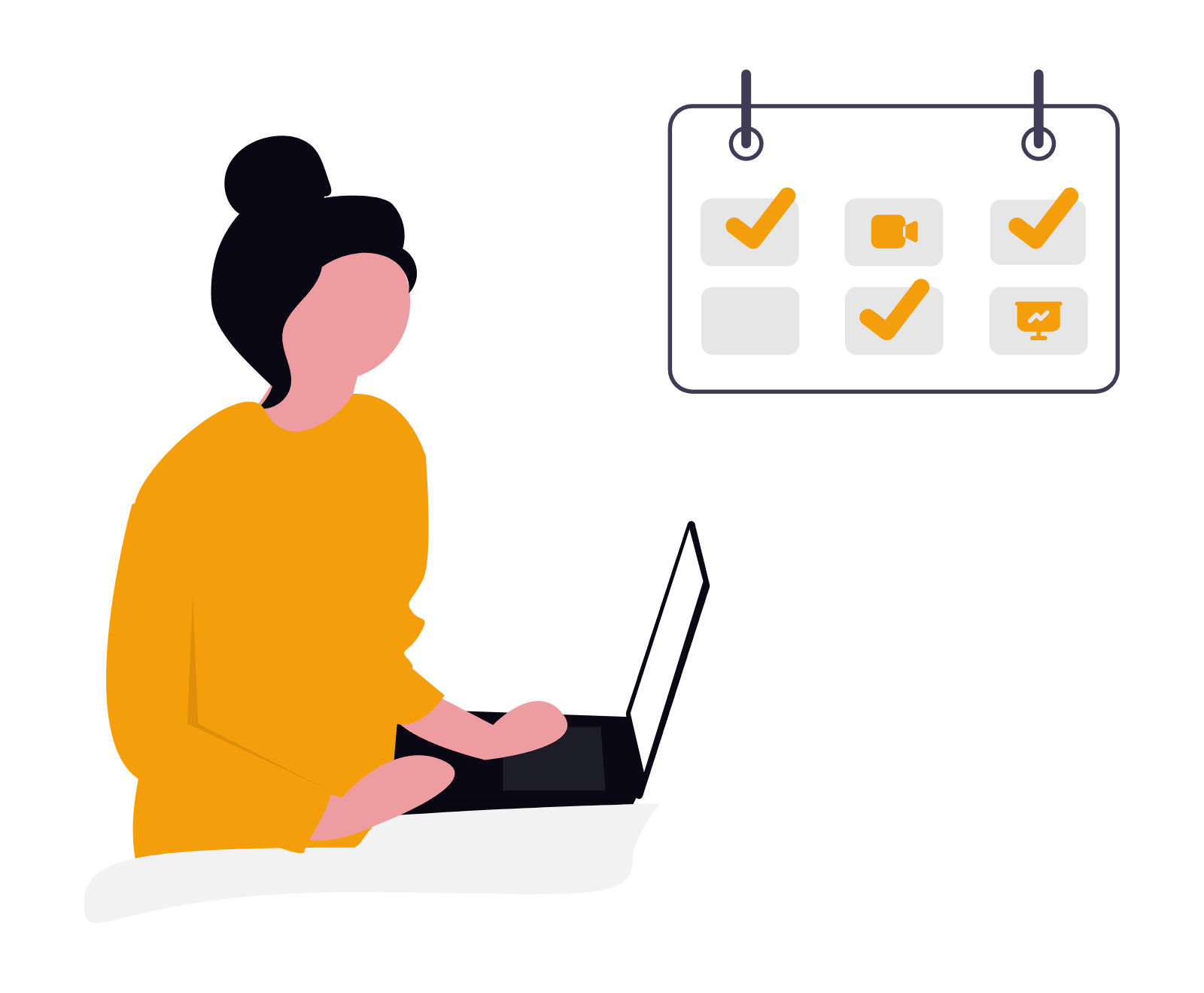
ここでは、なぜNewRelicの個人利用が難しいのか、その理由を解説していきます。
機能が広すぎて把握が困難
NewRelicは単なる監視ツールではなく、「APM(アプリ監視)」「インフラ監視」「ログ」「トレース」「ブラウザ監視」などの統合プラットフォームです。
そのため、データやメトリクスの取得は簡単なのですが、取得後の解析・理解が最大の壁になります。
私はインフラエンジニアをメインに活動していますが、アプリケーションの改善をしようとすると、DBのカラムやバックエンド側のログの読み込み・解析をしなくてはなりません。
「取得は簡単だけど、それを修正するスキルがない」という感じです。
やれることが多すぎて、一人では手に負えない状況となってしまいました。
アラートチューニングの難易度
監視の精度を高めるには、アラート条件の細かな調整が不可欠です。
たとえば、AWS EC2のCPU使用率や応答遅延を監視する場合、しきい値を誤ると「通知過多」または「重要な異常を見逃す」事態に陥ります。
実際、筆者も初期設定のままでは通知が乱発し、Slackがアラートで埋まりました。
ダッシュボード設計に知識が必要
NewRelicはデフォルトで豊富なダッシュボードを提供しますが、一部はユーザー側でカスタマイズが必要です。
NewRelic独自のNRQL(NewRelic Query Language)を理解し、「どのメトリクスを」「どんな条件で」表示するかを自作する必要があります。
これが一人情シスやフリーランスにとって大きな負担になります。
個人導入の限界と現実的な活用法
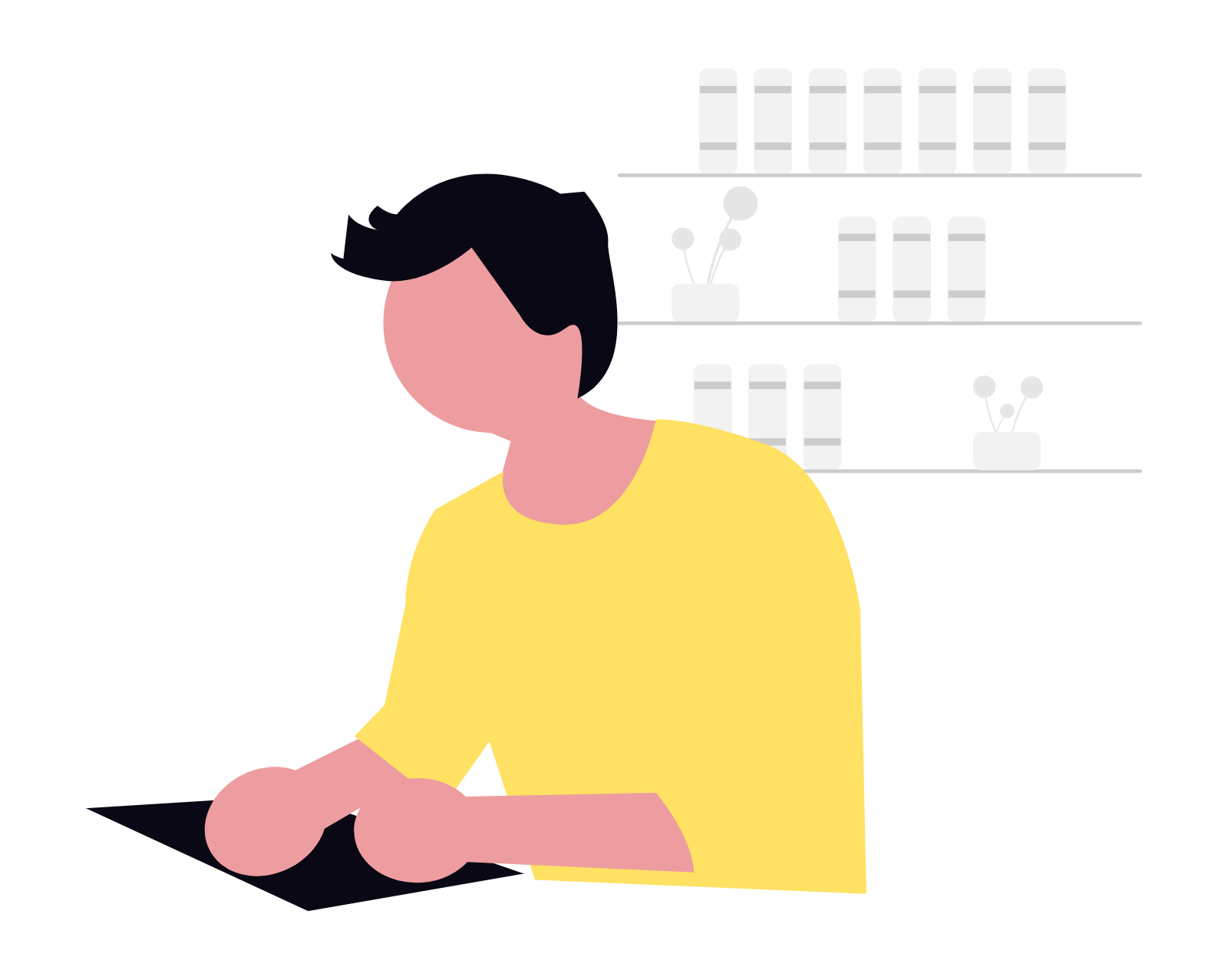
結論として、NewRelicを個人で導入することは可能だが、継続運用には複数人の体制が望ましいというのが実感です。
無料プランでもSLAやクリックログのトレースなど、AWSのサービスだけでは実現できないことも簡単に導入できることは確かです。
しかし、分析・調整・運用改善をすべて一人で担うのは、時間的にも知識的にも負担が大きくなります。
一人情シスやフリーランスが取り組むなら、以下のような活用が現実的です。
- 学習・検証用として使う:監視設計やメトリクス理解の練習環境に最適。
- 限定的な範囲で可視化する:EC2やRDSの主要指標だけをNewRelicに統合する。
- チーム導入のためのPoCに活用する:将来の監視基盤整備に向けた検証として使う。
NewRelic 個人導入は、万能ではありません。
しかし、「AWSをより深く理解し、監視設計を体験する」うえでは、これほど学びの多いツールも珍しいでしょう。
もし本格運用を目指すなら、まずは個人で試し、次にチーム導入を見据えて拡張する。
このステップが、最も効率的でリスクの少ないアプローチです。
