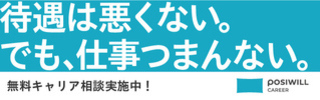滋賀県職員の部長によるパワハラのニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20230210/2060012662.html
滋賀県は部下のが作った資料について2-3時間にわたって問い詰め、資料を複数回作り直させるなどのパワハラ行為を行ったというニュースがありました。
パワハラの類似体験談
このニュースを見て、筆者自身も似たような体験をしたことを思い出しました。
実際には私の体験ではなく、私と同じプロジェクトに入っていたメンバーの体験談となります。しかし、同じプロジェクトメンバーとしてこのパワハラによりプロジェクトに遅れが出たことは事実です。
現在の社会はこのようなハラスメントが身近にあるということを知ってもらいたいと思います。
登場人物
ITインフラの中小企業
工事部部長:プロジェクト主管部署の部長。プロジェクト自体の主管部署ではあるが内容は把握していない
工事部メンバー:工事部側担当社員。
技術部次長:プロジェクトの技術部門の一番階級が高い人物。今回のパワハラを行う人物。気分屋、上下関係に厳しい。工事部部長とは過去に上司部下の関係だった時期もあり。工事部メンバーのことが嫌い。
技術メンバー:技術部側担当社員。私。途中までプロジェクト参画していたが途中退職。
プロジェクト概要
DX化による紙媒体の受け渡しを無くす電子化プロジェクト。工事部門で工事管理〜工事担当へ紙での指示書受け渡しが発生するため、それを電子化して効率化する目的です。
工事発注にはフロー内に技術部門の確認等が発生するため、技術部門も参画していました。
パワハラ内容
工事部メンバーの資料が技術部次長に承認されない。
プロジェクトの説明資料を作成し、技術部門側のフロー変更が発生するという旨を説明したところ、技術部次長が許可をしませんでした。
何かと理由をつけて工事部メンバーの作成した資料に許可をせず、プロジェクトが進まなくなりました。
他の業務と並行に動いているため、1ヵ月半程度プロジェクトが遅れてしまいました。
資料自体は至極まともな資料で、私自身も見ていて問題ないと思った資料でした。
どう解決したか
工事部メンバーが工事部部長を同伴させて同様の資料説明をしたところ、何の問題もなく技術部次長側が許可を出しました。
技術部次長は内容云々ではなく、工事部メンバーが嫌いというだけで許可を出さなかったようです。
技術部次長と上司部下の関係があった工事部部長を通して話すと、次長側は途端に腰が低くなり、「あ~!そんなことなんですね~!!その案でいきましょう!」とすんなり許可が出たそうです。
このように、人の好き嫌いで仕事を進める人が存在するということです。
技術部次長の年齢は当時48歳でした。
まとめ
滋賀県職員によるパワハラと似たような体験談をご紹介しました。
このように、現社会には残念ながらこのような私情を挟んだ、好き嫌いで物事を判断する人が管理職になっている会社が往々にあります。
このことをさらに上の上司に報告したところで、その上司も技術部次長と数十年の関係を崩したくないのか対策をしません。
結局、現在も技術部次長はその職で働いており、何も変わらず過ごしています。
若手社員や部下のメンバーは次長の異動や定年退職を待つしかない状況となります。
状況を変えるには転職しかない
このような状況に陥った場合、残念ながら短期的な解決は不可能です。会社側も処罰は厳しく、中長期的に異動や退職を待つしか方法がありません。
短期的に解決をするには自分が異動をしたほうが手っ取り早く済みます。
現代は転職が当たり前となっており、前職よりも年収が上がる場合や職場環境が良くなる可能性があります。
「POSIWILLCAREER」をご紹介します。下記となります。
「POSIWILLCAREER」は、20-30代に特化した、キャリアのパーソナルトレーニングです。転職エージェントではないので、転職先を紹介するだけではなく、どう生きるかの整理をすることをサービスの主目的としています。
1. 転職サイトや転職エージェントだけでは解決し切れない、キャリアの軸や強みを明確にする。
「自己分析」や「キャリア設計」、「転職活動サポート」を徹底的に行い、理想の転職・生き方へと導くためのサービスを提供しています。「活躍できる」且つ「採用される」企業・適職の選定まで可能なので、「どう生きたいか」という人生の軸をベースに、中長期的なキャリアを設計することが出来ます。
2.短期集中的に自己分析から求人探し・応募まで徹底的に伴走するトレーニングシステム。
トレーニングプランは複数ありますが、共通するのは人生(キャリア)の軸を作ることです。無料カウンセリングを入り口として、卒業までマンツーマンでパーソナルトレーニングを行います。
法政大学キャリアデザイン学部「田中研之輔」教授がプログラムを監修し、専門的知見を織り交ぜてトレーナーの育成・研修やプログラムの設定を行っています。キャリア論の専門的知見と、キャリア相談の経験的実績を総合的に分析しながら、1人でも多くの方が「自分らしい働き方」を見出す機会を創出していきます。