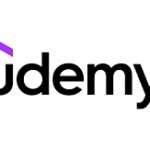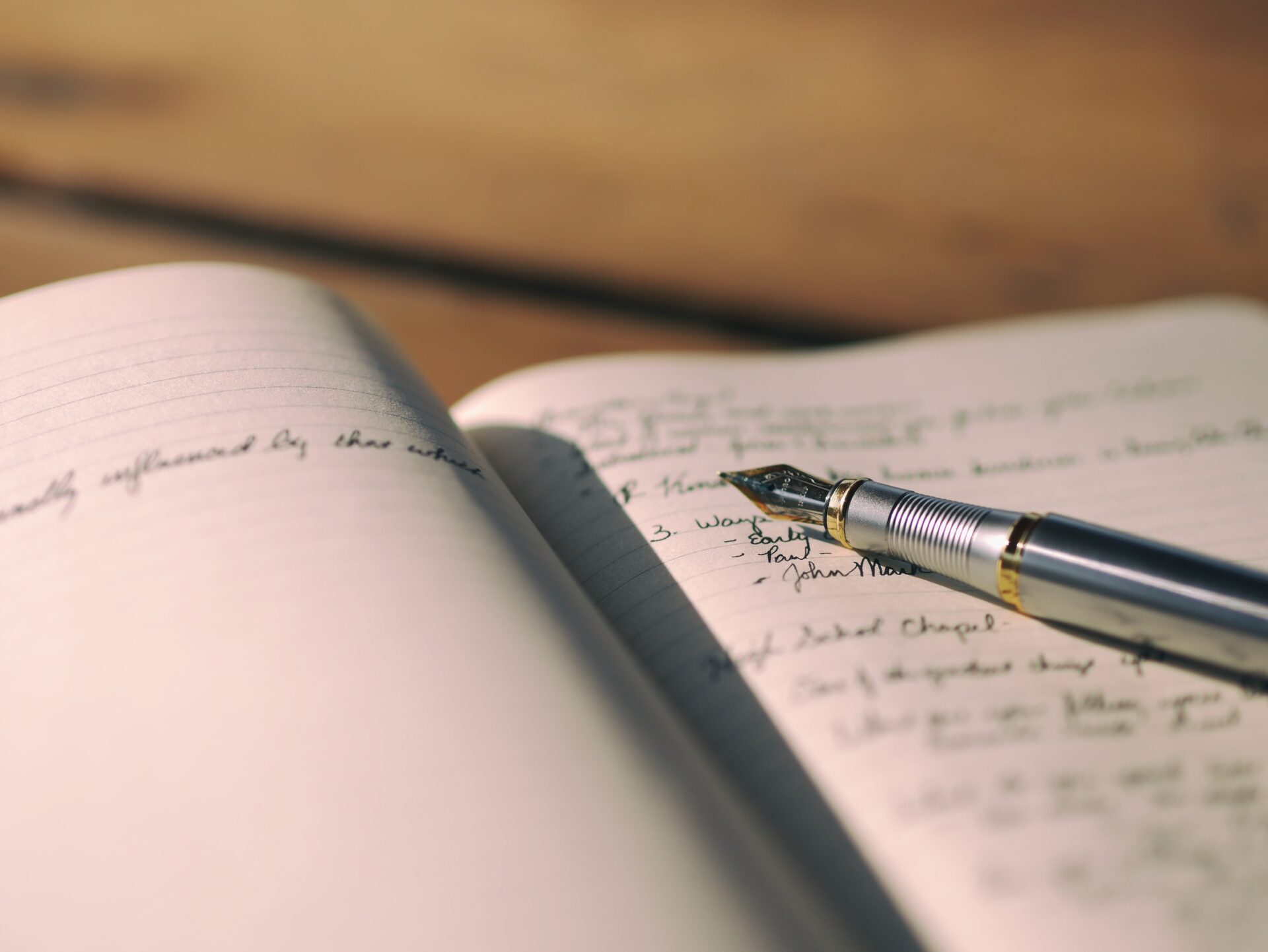
Route53
Route53はAWSのマネージドDNSサービスで、ドメイン名のレジストラとしても利用できます。ドメイン名を管理し、DNSレコードを設定することができます。また、Amazon EC2、ELB、S3、CloudFrontなどのAWSサービスとの統合も容易です。
今回は、ホームページ公開やアプリケーション公開時に設定する、DNS設定でRoute53の設定は必須か否か、メリットデメリットについてご紹介します。
Route53は必須ではない
結論からいうと、Route53は必須ではありません。他会社のDNSサービスを利用してAWS上のリソース(HP・APP)を公開することができます。
しかしRoute53を利用する上で、メリットもあります。(デメリットもあります)
Route53を使わずに公開する方法、Route53のメリット・デメリットについてご紹介します。
Route53を使わない方法
Route53を使わずに、お名前ドットコムやさくらインターネットのDNSサービスを利用してアプリケーションを公開することが可能です。
DNSは「NSレコード」というものに従ってドメインのルーティングを行います。
NSレコードをAWSのDNSサーバーにするか、お名前ドットコムやさくらインターネットのDNSサーバーにするかの違いとなります。
機能としてはほとんど変わりありません。
お名前ドットコム内のDNSレコードを使ってAWS Lightsailで本ブログを公開しています。
https://www.kaitech-media.biz/post-215/
NSレコードは、お名前ドットコムのサーバーを指定、ドメインのCNAMEはAWSのCloudFrontを指定しています。
ACMの証明書もCNMAEで登録しています。
お名前ドットコムの登録は下記から可能です。
Route53をDNSで使うメリット
Route53は必須でないにしろ、使うとメリットはあります。
AWSリソースに対してレコード変更の浸透が早くなる
NSレコードをAWSのDNSサーバーとして指定している場合は、AWS他レコードも、NSレコードもAWS同士であるため、浸透時間が早くなる可能性が高いです。
AWS公式では数時間~数日と書いてありますが、実際はレコード変更後の数分~数十分で浸透・反映されます。
他サービスだと、AWSのレコード仕様と他サービス側のNSレコードの仕様があるため、浸透に時間が掛かる場合があります。
レコード変更する場合があり、断時間の許容が無い場合はRoute53を使うメリットはあります。
Route53からAWSリソースの登録が簡単
S3やALB、CloudFrontなどをRoute53で登録する場合、他サービスと比べると非常に簡単です。
レコードを登録する際に、カーソルを合わせ文字を入力すると、文字一致で既存リソースが表示されます。
下記の「レコードを選択」の部分にリソースがあれば表示されます。
該当のリソースをクリックするだけで設定文字列が入ります。
※EC2など一部は未対応
SESやACMの場合は、Route53に自動でレコードが追加されます。手動でのRoute53操作は不要となり、便利です。
下記で「Route53でレコードを作成」とすると、自動でレコードを追加してくれます。
他サービスだと、レコード登録方法が異なる
お名前ドットコムやさくらインターネットでCloudFrontなどのCNMAE登録をする場合は注意が必要です。
AWSのRoute53で登録する値とは文字列が異なる場合があります。
仕様によるもので、VALUEの値の最後に「.(ピリオド)」が付く場合や、逆に付かない場合、VALUEの値の文字列が一部不要(既にサービス側で自動入力されるため不要)だったりします。
浸透に時間がかかるため、設定に躓いた場合時間がかかってしまいます。
Route53を使うデメリット
Route53の料金が発生する
Route53でレコードを管理すると料金が発生します。
https://aws.amazon.com/jp/route53/pricing/
お名前ドットコムやさくらインターネットの場合は無料であるため、この点はデメリットです。
Route53で購入できるドメインが高額
AWS Route53からドメインを購入することはできます。しかし他に比べると高額です。
また、インターフェースが使いづらく、初心者には登録が難しいかもしれません。
設定画面の説明が不十分であるため、設定ミスが起こる場合があります。
AWSの効果的な学習方法は?

最後に、AWSの効果的な学習方法をご紹介します。
自学自習はUdemy講座
オンラインプラットフォームであるUdemyは安価で手軽にAWSの学習が可能です。
しかし、上記で紹介したような実際のAWSエンジニアが実施している構築スキルまでは教えてくれません。初心者~中級者向けの講座が多くなっています。
私も受講した、初心者向けAWS講座を下記記事でまとめています。ご参考ください。
1人で学習が難しい場合はオンラインレッスン
1人で学習が難しい場合はオンラインレッスンがおすすめです。
最近では、AWS講座を提供するオンラインレッスンも増えてきました。
料金は高くなりますが、現役エンジニアからAWSについて学ぶことができます。
本ブログ執筆者のメンタリングも受付中
本ブログを執筆している[KAITech]もメンタリングを受け付けています。
オンラインレッスンは高くて手が出せないという方は私までお気軽にご相談ください。
下記から承っております。