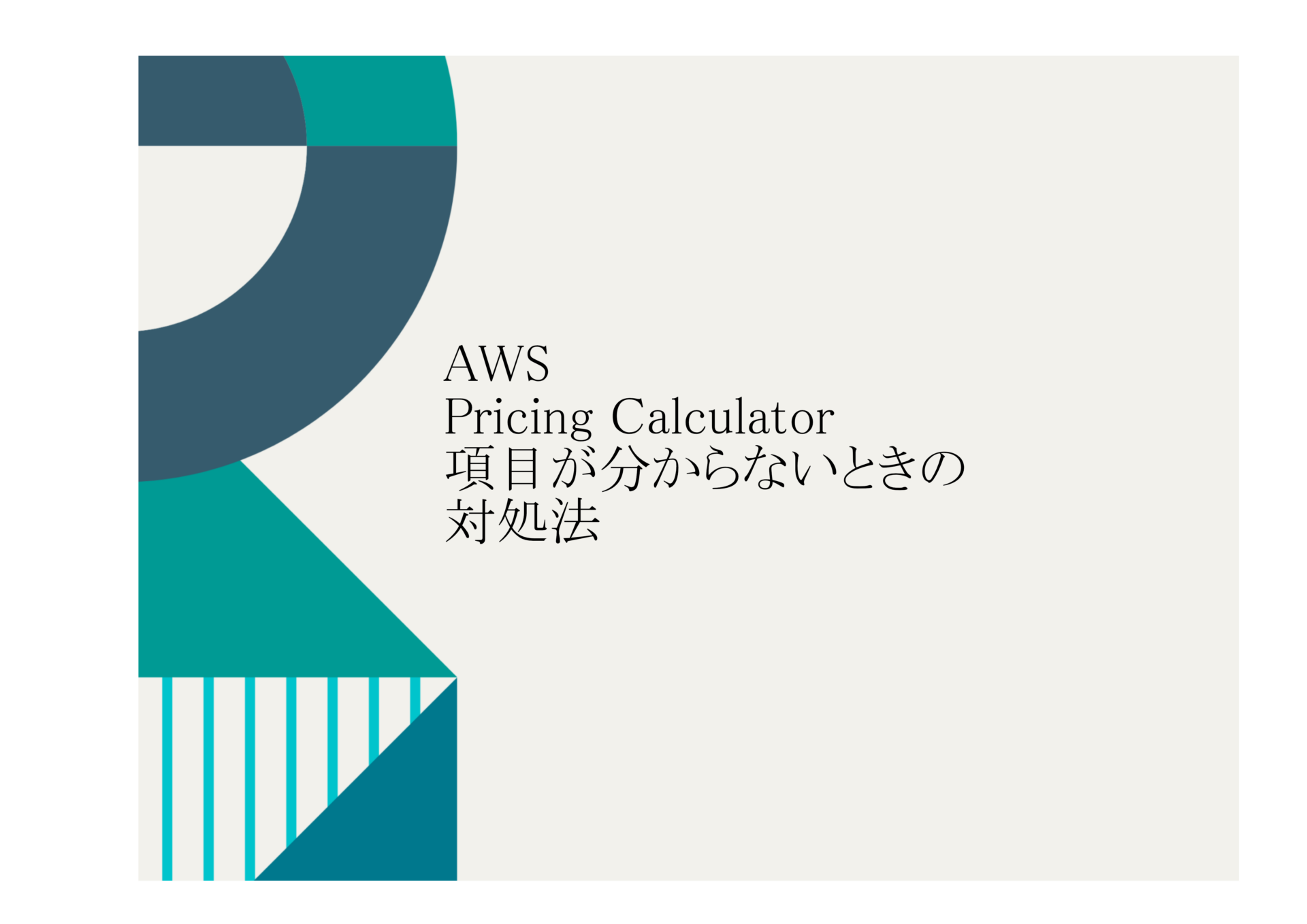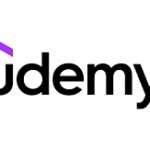AWSの見積もり、Pricing Calculatorの項目が分からない!

AWS Pricing Calculatorは、AWSの各種サービスを利用した際の料金見積もりを簡単に算出することができるウェブベースのツールです。サービスの使用量やリージョン、オプションなどを入力することで、各サービスの利用にかかる料金を計算し、比較することができます。また、複数のサービスを組み合わせた場合の総合的な料金も見積もることができます。
しかし、このAWS Pricing Calculator、初心者には設定が難解だと思います。
実際に構築している人ですら、「この項目何入れるの?」という項目が多数あります。
そこで、今回はこのAWS Pricing Calculatorの使い方とコストの整合性についてご紹介します。
公式ではありませんが、別の方法でも概算見積もりを出すことも出来ます。併せて紹介していきます。
公式見積もりツール:Pricing Calculator
まず、Pricing Calculatorのアドレスは下記です。
このサービスはAWSアカウントを持っていなくても、どなたでも利用可能なweb上のサービスです。
AWSの見積もりが必要なシーン
前提知識として、AWSは従量課金制のサービスです。初期費用(イニシャルコスト)はなく、使った分だけ費用が発生します。
一般的に、組織で利用する場合は、会社としては予算を組んでからAWSの利用を開始するという流れになることが多いでしょう。
上司から「AWSの費用を見積もれ」と言われても、従量課金制のため費用を見積もる部下側の立場になると難しい話となります。
部下の本音としては「使った分だけかかるので、分かりません」と言いたいですが、社会人としては数字を何とか出さなければいけません。
そこで、Pricing Calculatorを利用して概算費用の見積もりを出します。
AWS見積もりツール Pricing Calculatorの使い方
上記のアドレスから、見積もりを作成していきます。
①「見積もりの作成」をクリック(初回は英語の可能性があります、右上から言語の変更が可能です。)
②「サービスの追加」をしていきます。
③リージョンを設定する該当のリージョンに変更して、利用する予定のサービスを選択して見積もりを作成していきます。
④今回はストレージサービスである「S3」を例にします。「説明」は自分のメモ書きなので記載無しでも構いません。
S3のストレージクラスや保存量、データ転送量を入れていくと、自動で計算され見積もりが完成します。S3の見積もりが完成したら、「サービスを保存して追加」を押して、
他の利用する予定のサービスがあれば同様に実施していきます。
AWS見積もりツール、Pricing Calculatorの項目がさっぱり分からない!
上記のS3の場合では、下記の項目数があります。
- リージョン
- ストレージクラス(Standard / Intelligent / One Zone / Data Transfer / etc…)
- 保存するストレージ量(GB/月)
- PUT/COPY/POST/LISTリクエスト数
- S3 Selectによって返されるデータ量(GB/月)
- データ転送量(GB/月)
正直、見積もりの段階では仕様も何も決まっていないでしょうし、分かるわけない項目ばかりです。
AWS初心者の場合はストレージクラスも分からないので、どれにチェックをすればよいか理解できないと思います。
そこで、項目が分からない場合の対処法をご紹介します。
Pricing Calculatorの細かい項目は適当に入れても構わない!
Pricing Calculatorを使う場合の項目で、分からない項目は「0」でも「100」でも適当に入れても問題ない項目が多いです。
理由は、コストが安い為、0でも100でも誤差で数銭円しか変わらないためです。1円にもならない項目が多数あります。
試しに、項目を入れてもらうと、分かると思います。
パターンA:S3のPUT/COPY…のリクエスト数、100の場合の費用は「0.00USD」です
パターンB:続いて、1000にした場合、0.01USD(1円程度)です。10倍にしても1円しか変わりません。
このように、小さいシステムの項目によっては10倍程度にしても数円しか変わらない項目があります。
よって、よく分からない項目は適当に数字を入れて料金の上がり具合をみて無視しても問題ないと思います。
AWS公式サービスではないが、「ざっくりAWS」を使う
公式ではありませんが、下記コストを見積もることができるサイトがあります。利用料は無料です。
日本人のために作られたサービスで、使い勝手がよいサイトです。
対応していないサービスがあること、日本円で表示されるため、Pricing Calculatorと併用するとJPY/USDが混在して見づらくなることが注意です。
また、項目数もPricing Calculatorに比べるとかなり少なく、ざっくりした費用感が分かります。
項目数が少ない為、Pricing Calculatorよりかは精度は低いですが、小さいシステムであれば誤差は正直数十円~数百円程度だと思います。
AWSの資格:AWS Certified Cloud Practitionerレベルの知識を持っておく
一番は、AWSの学習をすることです。専門的ではなくとも、AWSの初級試験であるAWS Certified Cloud PractitionerレベルがあればPricing Calculatorが使いこなせるようになると思います。
AWS Certified Cloud Practitionerは知識がない状態でも1~2ヵ月程度で取得できる資格です。
私の合格体験記はコチラです。
この資格を学ぶことで、S3の場合はストレージクラスの種類とその金額感(どちらがコストが高いか低いか)が分かります。EC2やRDSも費用感覚が身に付きます。
公式ページを確認する
S3だと下記です。「[サービス名] 料金」で調べると大体検索エンジンの1番上に表示されます。
https://aws.amazon.com/jp/s3/pricing/
ここに項目内容の説明と料金が書かれています。
項目説明が分かれば、どれを選択すれば良いかの材料になると思います。
料金表があるため、見積もり後に費用が高かった場合には料金表からもう少し安い設定を確認することもできます。
AWSの効果的な学習方法は?

最後に、AWSの効果的な学習方法をご紹介します。
自学自習はUdemy講座
オンラインプラットフォームであるUdemyは安価で手軽にAWSの学習が可能です。
しかし、上記で紹介したような実際のAWSエンジニアが実施している構築スキルまでは教えてくれません。初心者~中級者向けの講座が多くなっています。
私も受講した、初心者向けAWS講座を下記記事でまとめています。ご参考ください。
1人で学習が難しい場合はオンラインレッスン
1人で学習が難しい場合はオンラインレッスンがおすすめです。
最近では、AWS講座を提供するオンラインレッスンも増えてきました。
料金は高くなりますが、現役エンジニアからAWSについて学ぶことができます。
本ブログ執筆者のメンタリングも受付中
本ブログを執筆している[KAITech]もメンタリングを受け付けています。
オンラインレッスンは高くて手が出せないという方は私までお気軽にご相談ください。
下記から承っております。